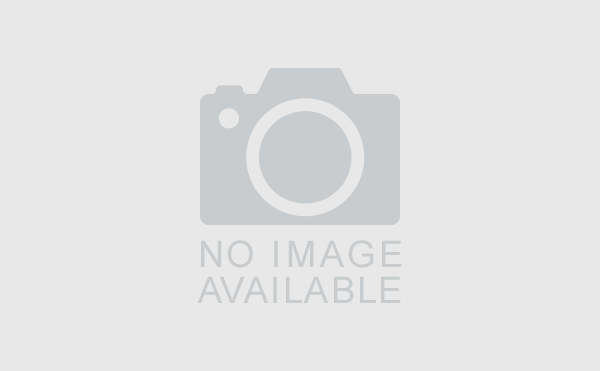はじめに
生成AIの発達は,凄まじいものがあり、日常的なことさえ,人の代わりにやってくれるようである。従って、AIにそれらの技術を教える学校の様な所も不可欠で有るという。ただ,現在のAIは、文字の知識で学ぶだけで、人間の様に五感での経験が殆どないのが課題であり、人間の脳と比べて効率も大変悪く,電源の課題も解決する必要があるとのことである。
また、戦争の為のAIは,作ってほしくない。
①公的支援策の紹介
国や自治体が,何かしらの困難を抱えている人を支援する施策を作っているにも関わらず、必要とされる人へ届かない、と言う話を聞く。支援を受ける為の申請や制限など,複雑な仕組みが有るからかも知れない。そこでAIが、その人の困難さを対話形式で聞き出し、適当な支援策を利用者に通知すると共に、その支援を利用者が受けたい場合には、申請の手助けなどをする仕組みが欲しい。
②悩み相談
AIが人を孤立させない為に,相談相手になる,と言う仕組みであり、生成AIによる,多様な支援が可能ではないかと、いくつかの例を紹介している。
<ITアドバイザーの地域ごとの設置>
折角、良いAALシステムを作っても,その利用者が快適に継続して使ってもらうには、利用者と伴走してくれる身近なITアドバイザーが必要である。
<あたたかい手ーAAL支援チーム(6)知的障がい者の支援>
・先月号迄のあらすじ
平次とあけみは、古谷真理子の勤めている知的障がい者の施設,オリーブを訪問して、施設長と真理子から施設の概要と利用者の困難さなどの説明をうけた。
・施設内を就労支援Bチームと廻る
平次とあけみは、リーダーの黒田さんの説明を聞きながら、Bチームが施設を清掃しながら廻る作業に付き添って,施設内を見学した。
ショートステイの清掃に入った時は、利用者がゴミ箱に吐いた汚物があり、騒ぎになった。そこで、Bチームが,日常的でない事に出くわすと、正常な状態にならないと言う困難さがあることを平次とあけみは理解した。平次は、具合の悪かった利用者の見守りが不十分であったことから、この施設にAALシステムの導入を提案したいと真理子に告げた。
おわりに
AALシステムの理想的な運用は,自宅、屋外,施設などで,24時間365日シームレスに行うことである。その為には、国内での標準化での普及が必要であると思う。
それと,筆者は、放送大学でのリハビリテーションの科目を受講する事にした。まだ、まだ、である。