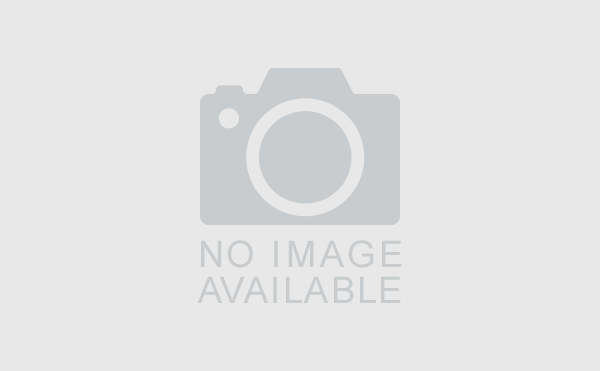月刊自動認識2025年10月号(第53回)の概要
はじめに
筆者の友人が、脚立で作業中に落下して気を失い救急車で運ばれて,約1ヶ月入院して回復してきたので,筆者の留守電を聞いて、電話して来たとのことでした。長い間,ベッドで寝ていた為に,体が思うように動かないので、その時は、この病院を退院したら,リハビリ病院に転院すると言ってもいたが、一週間後に、リハビリ病院には行かなくても良いとの医師の見解で、その後、家で自分で歩く練習をしたが、回復は大変であったとの事であった。長期間ベッドで過ごした事から、多分HAD(Hospital ization Associated Disability: 入院関連機能障害)になったのかも知れない。何とか良い解決策を考えたい。
AAL(Active Assisted Living: IT機器で日常生活を支援)のユースケースを小説風に書いた。
・あたたかい手-AAL支援チーム(5)知的障がい者の支援
前回迄のあらすじ
角川病院長からの提案で、太陽プロセスの西田取締役とのHADの対策プロジェクトが発足した。病院,介護施設、保健所,自治体が一体となったチームで対応することになってオンライン会議が始まった。
初めての会議なので,角川病院長のプロジェクトの目的の説明が有り、自己紹介と関連する事例などが話し合われた。最後に保健師から,リハビリで多少問題のある古谷さんと言う人を尋ねることを平次が引き受けてしまった。
知的障がい者利用施設の見学
古谷さんとは何とか良い話し合いが出来たが、古谷さんの娘の真理子さんが勤めている知的障がい者の利用施設を見学して、彼等が将来,両親などが亡くなった後でも生活ができるようにAALシステムで支援が可能かを,平次とあけみで調査することになった。施設長と真理子から,知的障がい者の状況の説明を聞いた後の昼食後に施設内を見学することになった。(続く)
おわりに
電気自動車の普及で,走行音がとても静かになり,特に視覚障がい者が接近に気づかないと言う問題があり、各社が異なる音を付けているが,統一を望む声が上がっている。筆者は、電動アシスト自転車も何らかの方法で、接近がわかると良いと提案している。