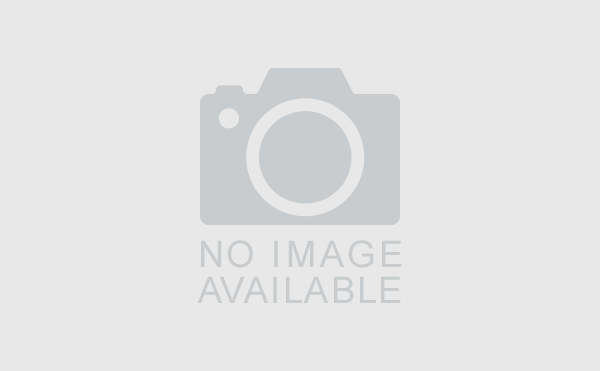月刊自動認識2025年9月号(第52回)の概要
はじめに
筆者は毎年の様に,なんらかの病で入院しており、日常生活の当たり前が,当たり前では無い事を感じている。中野玄三さんが、ALSを罹患し,手が自由に動かせなくなったときに、ネガティブな考えでは無く、自分の手の代わりに、他の人々の手を借りて、今迄と余り変わらない生活していくことを考えた,と言う話であった。筆者がめざしているのとかなり似ており、筆者は人の手が届きにくい所にIT機器で支援する事を考えているのである。
あたたかい手ーAAL支援チーム(4)
1. 古谷宅への定期メンテナンス
古谷家の玄関のインターフォンを鳴らすと、いつもと違う、女性の声で応答があった。古谷賢治さんの娘の真理子さんであった。風邪気味の古谷さんと炬燵に入りながら、世間話をして、この地区のAALシステムの稼働状態を聞き出すと、隣の齋藤さんが血圧計がおかしいと言ったので、古谷さんの持っている血圧計で測ると、AALシステムの値とそう変わらなかった。このような、ちょっとした心配事でもすぐに相談できる人が近くにいる事は、AALシステムの継続利用という事では,必要なことである、と考える。今回のメンテナンスは、リモートでも可能だが、平次は利用者と、実際に会うことで、より強い絆が生まれることやシステムの改善のヒントが得られる事を目的としていたのである。話が一段落したところで真理子がお茶を運んできてくれた。真理子が「このシステムは,素晴らしいけれど、私の勤務している知的障がい者や認知症の方にも利用可能なの」と平次に質問して来たが、平次は答えに窮した。
2.障がい者施設の訪問
翌年の2月中ばに、平次とあけみは、古谷真理子の勤務する知的障がい者の施設に平次の運転する車でむかった。(続く)
おわりに
妻の友人で,英国人の夫を持つ人が筆者宅に滞在した。彼女は,日本のカタカナ英語は,理解するのが難しい、他の言葉に聞こえてしまうとし、カタカナで書いた英語もなんだかわからない,とこぼしていた。まず,アクセント表記が無いし,誰かがつけたカタカナ英語は、まるで,理解出来ない事があるとの事。小学生から英語の授業が始まった事なので、全てでは無くとも、カタカナ英語の後ろに英語表記を付けるなどで、正しい言葉の伝達が必要かも知れないと思った。