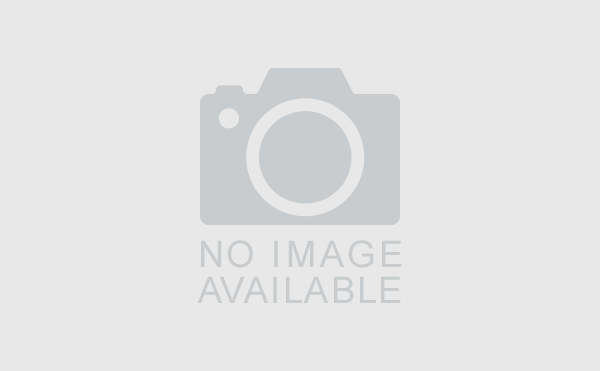月刊自動認識2025年8月号(第51回)の概要
はじめに
筆者は、また直腸ポリーブの切除手術で入院した。今回は腸粘膜の下にあるポリープなので、直腸の壁を削る事になると説明されて、血液をサラサラにする薬を服用していた為、出血を心配した病院は、1週間の入院となった。ここでの患者の薬服用の確認は、各薬の残数チェックであり、筆者のような前立腺と心臓の薬で6種類有るとかなり時間を要した。そこで、いくつかの、もう少し効率的な事を考えたが、今一よい考えが思いつかなかった。
<あたたかい手ーAAL支援チーム 第三回>
とくにシニアが入院して、長い間ベッドに寝ていると、歩けなくなったり、時には認知症が進むなどの治療目的とは異なる病状が起こる事(Hospitalization Associated Disability: HAD)があり、それをなんとか減らしたいと言う病院長の話から始まった。即ち退院後も自宅などで、リモートで体調のチェックやリハビリで患者などを支援するしくみを構築する話であり,チームがそれに、まず注力する事になった。話し合いの最後に,保険師から、一人の独居のシニアを訪ねてほしいとの要請があり、平次は、それを引き受けて、訪問する事になった。
その人は脳梗塞を患い右麻痺となった古谷賢治さんという方であった。彼は退職間際の罹患でショックを受けたエンジニアであったが、バイタル情報(血圧,体温,脈拍など)身につけるシステムを利用する事になって、介護,病院との連携で、バイタル情報を共有するシステムの試行実験に参加する事になった。リハビリにも参加していた。しかし,ある時、そのバイタル情報センサーが故障したが一品もので、修理は出来ず、代替品も無いという事で、古谷さんは,このシステムを信用しないだけでなく、関係者も,もう信用しないと言って来た。そんな人のことを尋ねる事になった平次は。続きは,本誌で。
おわりに
大部屋の方が部屋をでて、トイレや洗面に歩いていく事から、HADになりにくいのかもしれない。また、食事は、閉鎖された所でたべるのは、ちょっと寂しい。なんとかならないのか,と提案している。