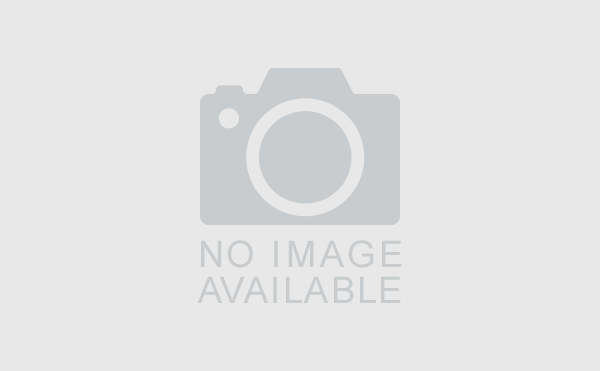月刊自動認識2025年5月号(第48回)の概要
はじめに
近年、日常生活での体調管理や運動時の活動測定なデータを得るためのウェアラブルデバイスの普及・利活用が急速に拡大している。利用者の見守りの為のAAL: Actine Assisted Livingでは、利用現場の保守・メンテナンスが容易な、日本からの新規国際標準としてIECに提案し、2021年から審議が始まり、ウェアラブルデバイスからのセンサ信号を共通的に処理できるよう、信号のやり取りを「コンテナ」化する技術仕様一連の策定作業を行いまとめられた国際標準規格が2025年2月に「IEC 63430:2025 (Data Container Format for Wearable Sensor)」として発行された。
<筆者がITで支援することで、ある人たちを避けていたこと>
この連載の初めの頃に「知的障がい、発達障がい、精神の病のある方等について話に、これらの人たちのIT機器での支援は無理だと思うので除外するとしたが、政府が「一人も残さないデジタル社会の創造」と言っているので、まずは、それらの病の人々の特徴を知り、支援のニーズを読者と共に学び、次に、それらのニーズに合わせたIT機器でどのような支援が可能かを考えてみたいと思う。
<APDの追加の話>
インターネットで、APDを検索すると沢山の関連記事がでてくる。APDの補完の説明。
<APDの症状を訴えた患者の半数以上が発達障がいがあること>
APDの症状の特徴である「ちゃんと聞こえているのに、相手の言っている言葉の意味が分かり辛い。」という、この症状を訴えた患者の半数以上が、自閉症スペクトラム障がい(Autistic Spectrum 以前はDisorders: ASDとも言われていた)・注意欠陥障がい(Attention Deficit Hyperactivity Disorder:ADHD/ Attention Deficit Disorder: ADD)、学習障がい(Learning Disabilities: LD)などは発達障がいと深い関係があると考えられている。
紙に書く事で聞く耳が持てる
「言葉は消えていっちゃうから、書いてほしい」
- 発達障がい(神経発達症)は生まれつきの脳機能の偏りがあるために、コミュニケーション能力、社会に関わる能力、学習能力、注意力」など、日常生活で求められる事柄に於いて、得意と不得意の差が大きく、特に不得意な事で日常・社会生活に支障が出てくるような症状が現れる事で「発達障がい」と判断される。
- 発達障がいは、知的障がいと混同されることがある。
- 発達障がいの特徴
<自閉スペクトラム症候群(Autism Spectrum Disorder: ASD)>
- 自閉スペクトラム症候群の特徴
おわりに
ここで述べた障がいがあっても、人はそれぞれのペースで成長していくものである。その人の特徴を活かした働きで、人生が送れる社会が来ることを期待する。