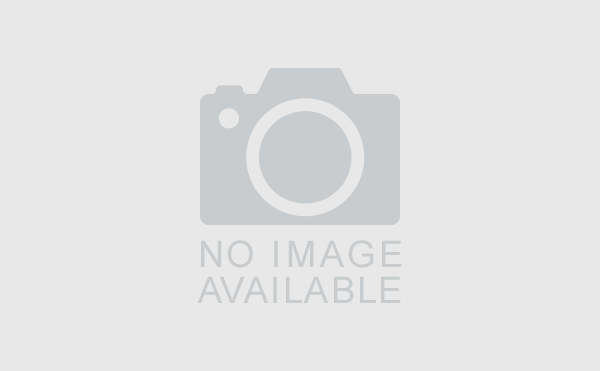月刊自動認識2025年4月号(第47回)の概要
はじめに
3月末で終わったNHKの朝ドラの「おむすび」に出てくる主人公の橋本環奈似の孫は、4月から看護大学に入学した。筆者の母、私の妻、長男の妻が看護師で、このまま行くと4代続くことになる。テレビの結は、病院の栄養士としてNST((患者の)栄養サポートチーム)として働くようになった。
NSTとは
栄養士、医師、看護師などの医療従事者からなるチームで、その患者の状況を話し合い、例えば、食欲のない入院患者の回復のために、患者の嗜好を聞きながら、栄養をも考慮して、食事を提供するチームのことである。
次は、また内輪の話ばかりで恐縮であるが、筆者の長男が世界医療関連5大機関誌の一つ数えられる医学誌にALS患者の呼吸リハビリの論文が掲載された事と、「おわりに」に紹介するALS患者のドキュメンタリー映画「はるかなる」を見た事で、筆者も、どんな病で、どのような支援が必要かを調べたみたくなった。
ALS(筋萎縮側索硬化症)
この病のでは、手足の筋肉の萎縮がはじまり、次第に肺の働きが悪くなり呼吸が困難で、以前は、この病の発症後、余命が3から5年と言う状況があった。しかし、現在では、肺の残存機能の維持の為に、肺容量リクルートメント療法を継続する事で、発症後数十年と命を保つ事が可能となった。
患者とのコミュニケーション
この病では、視覚、聴覚、脳の働きには、殆ど影響がないのだが、体の動作や発話が次第に困難になっていくことから、本人は、相手に意思を伝え難くなって来る。そこで、いくつかのコミュニケーションの方法が考えられた。
文字盤
一番簡単な方法は、患者と支援者の間に透明の板に書かれた文字盤を置き、その文字盤の上を患者の目線にある文字を支援者が認識して、読み進める方式である。
この方法は、相手と会話している感覚がメリットとなっているが、互いに慣れるまでは言葉の認識が難しいこととがある。
パソコン
同じように、パソコン上の画面に表示された文字、を患者の目線をカメラで追い、目を瞬きすることなどで確定する方式である。コミュニケーションの他に、メールなどの文章の作成が可能である。
ブレイン・コンピュータインターフェース(BCI)
患者の脳波を利用して、パソコンに文字入力してコミュニケーションをとることや、機器などの操作に使用するなどの魔法の様な事が出来る方法である。
頭に帽子の様な脳波センサーを被る方法と、脳内にセンサーを埋め込む方法がある。センサーを被る方は容易だが、ノイズの影響が大きく、更なる改良が求められている。また、センサーを埋め込む方式は、深度の脳波を取り込むメリットがあるが、これからの開発が始まるところとのことである。
ALS患者の呼吸の改善方法
LVRT(肺容量再活性化療法機器)の目的と効果
肺が膨らまなくなると呼吸不全となる。そこでLVRTで、肺の最大容量迄、空気を送り込みふくらます事で、肺の機能を保持する療法である。この方法では、酸素吸入も必要がいらない事例も多くあるとのことである。
おわりに
ALS患者の日常と心情を描いたドキュメンタリー映画であり、実際の文字盤による会話も映像の中にあった。私が驚いたのは、映画が終わった後に、その監督から年配のALS患者の奥様が自死されたと言う事であった。現在ALS患者は自宅でヘルパーさんによる24時間の介助が可能である。しかし、それが家族と患者との間を隔て、その奥様は「私は不要な人間」と感じていたかも知れないとの事であった。家族が介助から解き放されて、楽になったとは言え、矢張り何処かで家族が患者の介助や会話が出来る時間が必要なのかと思わされた事であった。